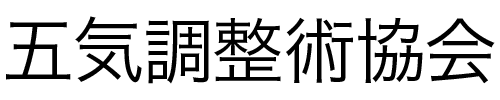「占い講座」のテキストを作ろう:「占い」の学びをワンランクアップする方法
「占い」を学ぶきっかけは、人それぞれだと思います。
でも、共通しているのは「占いが好き」だから。
「好き」なものは、もっと知りたいし、たくさん使いたい。
なので、本を読んだり、講座を受けたりして、学びます。
でも、学ぶほどに・・・分からなくなって
自信がなくなっていく。。。。
私もそう。
気が遠くなるほど昔から、たくさんの人々が、智慧を振り絞って、「占い」と向き合い、様々な「理論」が構築されていきました。そして、それは「現在進行形」でもあります。
なので、結局のことろは、「キリがない」わけです。
でも、そこがまた魅力でもあります。
なので、「占い」が好きな人は、超「オタク」系。
語り出したら止まらなくなる人だらけ。
でも、ある所まで「到達」すると、「スランプ」に陥るのです。
命式を観るほどに、何を観るのかがわからなくなる。それは、「焦点」が定まらなくなる感じのよう。そして、モヤモヤしてきます。「占い」が楽しめなくなってしまうのです。
これは、「学び」を一旦止めて、次の段階に入る合図なんです。
次の段階とは「伝える」こと。つまりアウトプットです。

アウトプットでお勧めの方法は、「講座」をする。
でも、いきなりそれは、ハードルが高いと感じてしまうかもしれないですね。
それでは、もっとハードルを下げて。
「講座テキスト」を作る。
「生徒さん」を想定して、伝えたい内容を、自分なりにまとめていく。
いつかきっと、まとめたものは、「世の中」に出ていくので、いつ出しても大丈夫なように、作りましょう。
こんなこと言われても、何から始めたら良いのか・・・・と思ってしまいますね。
それは、きっと、いきなり「文章」に取り掛かろうとしているから。
最初の一歩は、そこではありません。
最初に取り掛かるのは「目次」です。
まずは「大きい目次」を。
伝えたい内容の「見出し」を並べて書き出します。
「見出し」が揃ったら、順番を決めていきます。
できるだけスムーズに流れるように、「見出し」を並べ替えていくのです。
スムーズな順番は、
最初は「概要」、それから「概要」を膨らませる内容、それから「応用編」または「実践編」、最後に「言いたいこと」で締める。
こんな感じがお勧めです。
そして、流れが決まったら、それぞれの「見出し」に沿った内容の「項目」を書き出します。
ここまで来たら、「完成」まであと少しです。
「項目」を説明する「文章」を書いていきます。
全ての「項目」の「文章」が書きかがったら「完成」です。
「講座テキスト」が完成したら、それを読み返してみましょう。
自分の頭の中にあった知識を体系的に、見事にまとまっています。
何度も読み返してみると、「ここはもう少し深く書きたいな」と気になる箇所が出てきます。
そして、それを「学び」ます。
この段階は、次の「学び」に入ったので、今までとは全く違うはず。
きっと、今まで以上に「学び」が楽しくなりますよ!
この方法は、私のテキスト作りのやり方です。
一番最初に作った講座テキストは「習得ベーシックコース」のテキストです。
何度か修正を加えていき、今の形にとりあえず落ち着きました。


講座は「6時間」なので、内容を6つに分けました。
それぞれを「1時間」で行うように「文章」を書きました。
そして、最後の第7講座は「おまけ」の部分。「占い」を楽しく使いこなすための、ちょっとした「コツ」をまとめています。
最初に、「陰陽」と「五行」について。
それから、「十干」と「十干支」について。
ここまでは「概要」
そして、次に、それらを使って構成される「命式」について。
それから、次に、「命式」が影響を受ける「巡り」について。
そして、「これぞ四柱推命」と言える「大運」と「空亡」について。
これらが使えると、「イベント鑑定」は十分に行えると思います。

テキスト作りは、最初の「1冊」は大変。
でも、不思議と2冊目3冊目と、どんどん出来上がっていきますよ。
普段から、「学び」を資料にまとめておくと、それらを「合体」させるとテキストが完成するからです。
残念ながら、1冊目には採用されなかった資料は、次のテキストで、大事な項目になりますから。
それから、最後に。
もっとも重要なのことを。
「コピペ」は禁止です。ぜひぜひ、「自分の文章」でまとめてみてください。
「コピペ」は早いかもしれないけれど、不思議なことに、「コピペ」からは「2冊目」が誕生しません。
自分が生み出したものでないから、自分の手で育ていくのが難しいのです。
ぜひ、「マイテキスト」を作って!
「学び」をワンランクアップしていきましょうね。