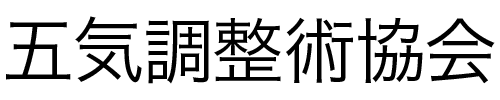「思い」貫くことと「思い」を手放すことに共通すること:タロットカード「ソード1」と「ソード10」:相反するもの中にある「点」
タロットカードは78枚あります。
「運命の物語」を提示してくれる、22枚の「大アルカナカード」と
「物語の楽しみ方」を提示する、56枚の「小アルカナ」です。
カードリィーディングで「大アルカナ」が出る「場所」では、「大きな節目や課題」を表します。
その周囲を「小アルカナ」が、道しるべのように、カード同士を繋いでくれて、「一つの物語」を読み取っていきます。
「小アルカナ」は4つの「象徴」があります。
・ソード(剣)・・・・・理性 知性
・ワンド(棒)・・・・・行動 情熱
・カップ(杯)・・・・・感情 愛情
・ペンタクル(コイン)・物質 財産
それぞれは、「1」が出発、「10」が「ゴール」です。
つまり「1」と「10」は、相反する「景色」を示しています。

「ソードの1」は、「理性・知性」の出発の「景色」です。
一本の「ソード」が天高く真っ直ぐに、突き立てられています。
背景の「灰色」はその「思い」の出発を、誰も祝福していないことを示します。一人で決めて、一人で始まった出発です。
握られた白い手は、何色にも染まらない「孤独」と「決意」の光で輝いています。そして、硬く力一杯、ぎゅっと握られていて、少しでも油断して手の力を緩めようものなら、剣がバランスを崩してしまう「不安定」な状態であることを表しています。
「灰色」の雲は、これから先の天気が、決して「楽観」できないことを教えてくれています。
そびえ立つ山々は険しく、それははるか彼方にそびえ立っていて、とても手が届きそうにありません。
でもわずかに見える「土」が
「しっかり考えて決めたことだから、自分を信じたらいいよ」
そんな風に、陰ながら応援をして見守ってくれています。
信じるものは、「自分の手の力」だけ。
ブレずに持ち続ける「覚悟」がないと、剣はたちまち揺れ始め、「王冠」が真っ逆さまに「奈落の底」に落ちてしまいます。
自分の「理念」を外に出して「形」にする時の「世界」を「ソードの1」が「景色」として表現しています。
実は、ソードの10枚のカードの中で、剣が真っ直ぐ上に向かって描かれているのは、この「ソードの1」だけです。
それだけ「思い」をしっかりと貫くのは、「勇気」と「覚悟」が必要なのです。
「ソードの3」を眺めていると、握りしめた白い手が、力を入れすぎて、頑張りすぎて、なんだかプルプルしているみたいで。
「ファイト!」
と応援したくなります。

「ソードの10」は、全ての「自らの理性」が、根こそぎ「否定」をされてしまった状態です。
それは、「外からの理性」に屈してしまった状態とも言えます。
カードリィーディングで、このカードが出た時、お客様の顔が曇ります。10本の剣が、全て「自分」に向かって刺さっている絵が、誰が見ても気持ちの良い気持ちにはなれるはずがないのも仕方のないことです。
背景は、全てを吸い込んで「無かったこと」にするかのように、真っ黒な空が広がっています。
その下には、「顕在意識の黄色」と「潜在意識の青色」の空はありますが、それらも全て「黒」が覆い尽くしています。
横たわっている若者は、情熱の赤いローブがかけられています。
でも、そのローブを、剣が鋭く切り裂いていて、剣は若者を刺しています。
若者をよく見てみると、不思議な事に気がつきませんか?
そうです。
右手が「Vサイン」をしています。
自分を祝福しているのか、まだかろうじて生きている「命」を祝福しているのか、それとも、刺されてもなを失わない「思い」を祝福しているのか。
何れにしても、全てはまだ、失くなっていません。
どんな状況に置かれても、それでも「私です」と言い切れる「思い」は、誰にも奪われないのです。
「ソードの10」は、悲しみと絶望の中でも、人は「希望」を失わない、「希望」の炎は消えることはない、と、教えてくれます。

かードリィーディングの解釈は、いく通りもあります。
カードの中の物語は、決して在り来たりなものではなく、観る人によって、「表」も「裏」も感じ取ることができます。
通常、「ソードの1」は、「ポジティブなカード」です。
でも、「出発」は、これから先、待ち受けている試練に向き合って、いかなくてはいけません。
それには、「敵」に攻撃を受けたり、疲れて休みたくなったり、誰かに頼りたくなったり。
そんなことが、これから先に次々と起こります。
「敵」の攻撃は、ある時突然やってきて、「傷」を負って、体も心もボロボロになってしまうかもしれません。
それでも、一人で、剣を掲げ続けることはできます。
諦めなければ。
「ソードの10」は、通常は「ネガティブなカード」です。
でも、裏を返せば、「外の理性」に全てを委ねた状態でもあります。戦うことを放棄して、全てを周囲の言いなりになると、もう誰からも刃を向けられることはありません。
自分で決断しなくても、周囲が勝手に決めてくれます。
自分で決めていないので、失敗しても、それは自分のせいではなく、周囲のせいです。だから、責任をとる必要はありません。
言いなりになっていると、ちゃっかり「おこぼれ」ももらえるかもしれません。「おこぼれ」がもらえたら、そっと「Vサイン」をしてみるのです。
組織の中で生きるのは、このほうが「楽」かもしれません。
でも、少しでも「自分の理性」が出てきたら、たちまち「傷」が痛み始めます。
だから、どんな時でも、何があっても「私は知りません」「私はわかりません」「私はできません」と、言い続けなくてはいけません。
どんなに「良心」の傷がうずいても、一人でそう言い続けることはできます。
諦めなければ。

「十二番目の天使」は、世界中で、最も多くの読者を持つと言われている、アメリカの作家 オグ・マンディーノの作品です。
「十二番目の天使」は、とても純粋で、とても前向きで、直向きに「生きる」ことにこだわります。
「十二番目の天使」は、「生きる」ことを、最後の瞬間まで諦めませんでした。
絶対、絶対、絶対、絶対、絶対、絶対、あきらめるな!
僕は、絶対、あきらめません。
天使は、いつもこの言葉を叫び、最後まで諦めませんでした。
だから、天使は、貫くことができました。
「ソードの1」と「ソードの10」は、「社会」の中で、自分の「思い」と向き合いながら生きる「両極端」の「景色」を見せてくれています。
自分の「思い」を外に突き出し進むのも
周囲の「思い」と同化して進むのも
覚悟を決めないと、一貫していくことは大変です。
覚悟が常に試されます。
でも、必ずできます。
諦めなければ。